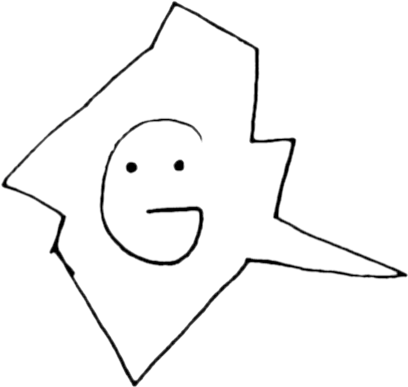
部下の教育で悩んでない?
- 言うことを聞かない部下を教育したい
- 受動的ではなく能動的なチームにしたい
- チームの雰囲気を一新したい

今回は、星寿美さんの著書「教育革命!小さな会社の自走組織の作り方」(発行:プラウド出版)で解決します!
自走型組織を作る手順
これまでの上からの指示に従う工場型教育の特徴は、「従順・勤勉・専門性」の3点を重視していたのに対して、これから必要になるのは自走型教育です。
自走型組織の特徴は、「主体性・創造性・情熱」と個人個人がそれぞれクリエイティブな思考を持って能動的に動きます。
工場型組織と自走型組織は延長線上には無く、全く別の路線に乗り換える必要があるのです。
ルールを1つ決める
ルールを1つ決めることで、自分の責任で自由に遊ばせて、刺激し合いながら自分も他人もNO.1を目指すことができます。
例えば、芸能マネージャーの仕事であれば「我々はタレントをサポートする集団である」というルールを設定することで、そもそも休みを求めるメンバーは入社しませんし、フレックスタイム制などの新しい働き方も生まれます。
この様に、1つのルールは浸透しやすく、メンバー個人個人に価値観を教育することができます。
ビジョンや理念を共感
自走型の組織を作るためには、メンバーの意識を変化させる必要があります。
「この仕事を選んだのはあなたでしょ?」とあくまでもアドバイスすることが大切で、「工場型を求めているなら他を探したほうがいいよ」などと、「自走型の会社を選択したのは自分である」と気付かせます。
社員の意識が工場型から自走型に変化することにより、それに伴って組織全体の理念も変化していきます。
関係性の質を高める
部下の「大丈夫です」は常に疑い、言葉通りに受け取ってはいけません。
部下が怒っている時、悲しんでいる時、あらゆる感情の「ありのまま」を受け止める場所やタイミングを作ることが重要です。
人間関係に問題が起きたタイミングは人間関係を見直すチャンスであり、部下の「大丈夫です」を疑い、ありのままを受け止めることが必要となります。
自走型を奪っていないか?
本書では、ビジョンや理念を教育することで、責任感を持って能動的に動く自走型の意識を持つメンバーに育つことが説明されています。
あくまでも「メンバーが自らの意思で行動する」ことが大切ですが、結局のところ、企業の理念を無理やりはめ込んでいる可能性は無いのか考えていきます。
企業側は自走型であって欲しい
そもそも、工場型のメンバーを雇用している場合、自走型の理念を無理やり教育するのは企業のエゴであり、気が付かせるのが間違いということも考えられます。
なぜなら、ブラック企業では洗脳に近い理念の共有が行われていて、メンバーは心身ともに疲労が蓄積し、最終的には精神的に苦痛を味わうことも十分に予想できます。
本書では、工場型と自走型は別々の線路と説明されていましたが、工場型の延長線上に自走型が生まれるカリキュラムを作ることができれば、ブラック企業化を予防する効果が期待できます。
自走型の機会を奪っている?
自走型は本人の意思を変えることが最も重要である点は、本書でも説明されていますが、教育をしている時点で本人の意思とは逆方向に向かっているのではないでしょうか。
そもそも、能動的に行動することは、本人が自らの意思で行動することであり、「本人の意思を変化させる教育」を行っている時点で、上からの指示に従う工場型と同等だと考えることもできます。
自走型の教育をすることが、結果的に自走型になる機会を奪ってしまっている可能性があるため、あくまでもキッカケを与える程度に留めておくことも大切かもしれません。
まとめ
管理職に従順な勤勉で向上心がある工場型の組織が主流でしたが、小さな会社こそメンバー自らが主体性を持って能動的に行動する自走型組織となるべきです。
自走型組織を作る方法として、
- ルールを1つ決めて価値観を教育する
- 自走型の理念を教育する
- 上司と部下の関係性を高める
以上の3点をご紹介しましたが、本書ではまだまだ具体的な方法が解説されています。
人材育成に興味があり、旧来の工場型から近未来の自走型を学びたい方は、ぜひ本書を読んでみてください!

最後までご覧いただき感謝です!

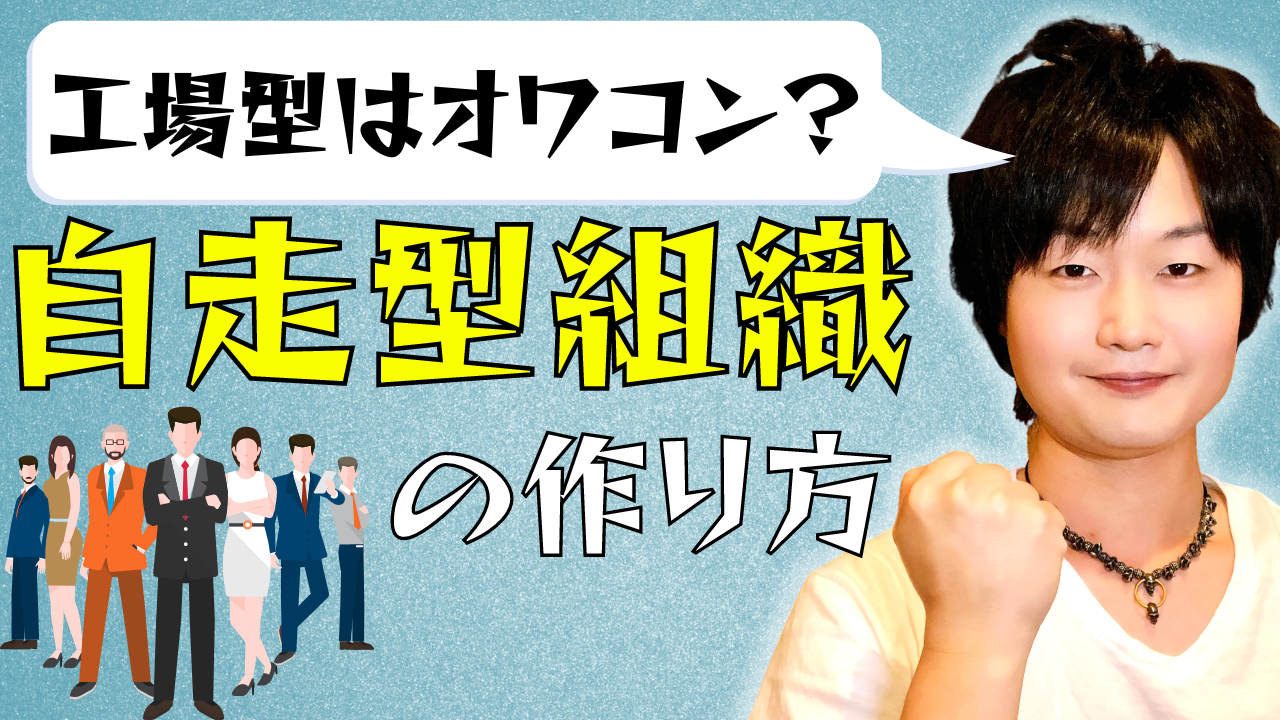



コメント