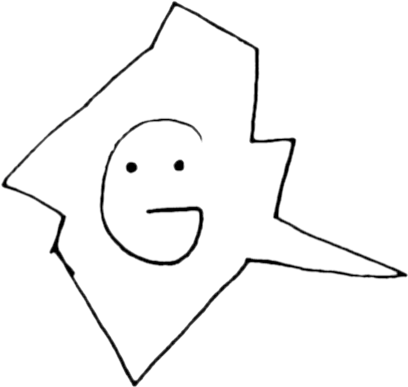
ナンバー2の役割で悩んでない?
- ナンバー2の立ち振る舞いが分からない
- 組織での立ち位置に困っている
- 自分の役割が分からない

今回は、トニーさんの著書「ナンバー2こそ自分のために生きろ!:〜ITベンチャーの経営で学んだ、組織の2番手としての役割〜」で解決していきます!
- 組織の中でナンバー2で振る舞いに悩んでいる
- 組織での立ち位置に困っている
- 自分の役割が何なのか分からない

3分程度でサクッと読めるので、ぜひ最後までご覧ください!
ナンバー2はトップと現場を繋ぐ
組織においてナンバー2の立場の役職に就いている方も多いですが、ナンバー2の立ち振舞によって現場社員の働き方にも影響をあたえます。
本書を読むだけで、ナンバー2の役割はトップの思考や目標を現場に繋ぐことが学べますので、部署やチームで二番手で活躍しているかたにおすすめの書籍です。
トップの思考を理解
基本的にトップは思考を言語化できない場合があるため、トップの思考を現場に伝えていく必要があります。
例えば、社長が「海外に進出するぞ!」と宣言したとしても、現場社員は「なぜ海外に進出?」といった疑問すら抱かない場合が多いのです。
ナンバー2がトップの思考を現場社員に落とし込み、現場社員の模範的な存在であることによって、トップの思考を共有することが大切となります。
現場の模範的存在
基本的に部下は上司の真似をしてしまうため、ナンバー2自身もトップの悪い部分は真似をせずに、現場社員のお手本となるような存在でなければなりません。
本書の例では、年上の新入社員にタメ口を使ったり、グループチャットで大勢の前で注意するなど、元を辿ると自らの管理能力の不足だと説明されています。
トップや上司の真似は時と場合により使い分ける必要性があり、自分自身で考えて行動し、現場社員の模範的な存在でなければなりません。
同情心は捨てる
トップは孤独に陥りやすい特徴があり、ナンバー2は唯一の理解者であろうと努力しますが、多くの場合は悲劇の始まりです。
「昔は苦労したから」といったような過去の苦労を理由にサポートしてしまうと、偏った組織になってしまう可能性があります。
ナンバー2は、トップと現場社員との間で公平性を保たなければならないため、同情心でトップをサポートしてはいけないのです。
ナンバー2は影の存在なのか?
本書では、ナンバー2はトップと現場社員を公平にサポートすることが、組織にとっては欠かせないことだと説明されていました。
ナンバー2はトップを支えるべき存在ではありますが、上層部である以上は表立って活動するべきなのではないか?と疑問に感じたため、果たしてナンバー2は影の存在なのか?について考察していきます。
性格による違い
私は、組織においてのナンバー2の立ち振る舞い方にも、性格によって種類があるのではないかと感がています。
主に、リーダーシップ型とサポート型の2種類のタイプに分かれます。
- リーダーシップ型…トップに変わって組織運営の実験を握っているが、最終決定のみトップが下す
- サポート型…主な方針や基本ルールはトップが定めて、ナンバー2はサポートに徹する
どちらのタイプかは企業の特性やトップの性格によって異なるため、これに従いナンバー2の立ち振る舞いも変化すると考えているのです。
土方歳三がイエスマンでなかったら?
ナンバー2がトップと反対した時点で組織として成り立たないですが、イエスマンであった方がトップの思考を現場社員に落とし込みやすさはあります。
ここで、幕末に活躍した新選組のナンバー2である土方歳三の例を参考にしていきます。
新選組では、ナンバー2である土方歳三が、トップの近藤勇に変わって、局中法度など様々なルールを制度かしていき、より強固な組織を作っていきました。
もしも、近藤と土方の方針が違っていたとした場合、組織は二分され、実際に新選組が創設された初期の反対勢力である芹沢派閥は近藤派閥に追い出されてしまったのです。
このように、組織のナンバー2は基本的にトップの思考を理解して、反対した時には組織が分裂することを意味するため、トップを中心として行動が求められます。
まとめ
本書では、ナンバー2の存在意義や立ち振る舞いが書かれていて、現在サブ的なポジションについてる人におすすめです。
組織においてナンバー2の役割の立ち振る舞いは、トップの思考や目標を理解して、自らの意思で考えて行動して現場社員のお手本とならなければなりません。
まとめると、ナンバー2はトップの考えを現場に落とし込む役割があり、
- トップの思考を理解する
- 現場の模範的な存在
- トップは同情心で助けない
以上の3点をぜひ仕事に落とし込んでみてください!

最後までご覧いただき感謝です!





コメント