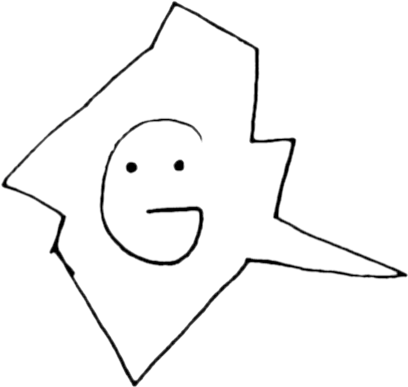
今回は、高橋洋一さんの著書「世の中の真実がわかる!明解 会計学入門」(発行:あさ出版)の書評だヨ

「BSとPLで企業の財務が見えてくる」でお馴染みの群馬俊貴です!
- 最低限の会計知識を身に付けたい
- 会社の財務書類を理解したい
- 会計用語の意味を知りたい

3分でサクッと読めるので、ぜひ最後までごらんください!
貸借対照表と損益計算書の違い
「会計学は何となく難しそう」という方々は、私含めて多いイメージです。
多くの社会人は、サラリーマンとしてのスキル向上のため英語を学び直す方が多いですが、会計学こそ社会人が学ぶべきだと本書では述べられています。
会計学を学ぶべき理由は、我々が暮らす資本主義社会では「お金の流れ」に人や企業のあり方が現れていて、会計学を学ぶことで人や企業の本質が見えてくるからです。
会計学で重要な言語は以下の2つです。
- BS:貸借対照表
- PL:損益計算書
BS/貸借対照表
BSとは通称バランスシートと言われる計算書であり、貸借対照表のことです。
右側に負債(必ず返すお金であり借金のこと)と純資産(貯金など返す必要の無いお金)、左側に資産(右側の負債と純資産を足したもの)が記録されています。
企業の財務情報を分析するときには、BSとPLのうち、まずはBS(貸借対照表)から見ていくのが基本であり、最も金額が大きい項目に注目することが重要です。
例えば、1億円で購入した不動産から得られる家賃収入や、高く売ったときに発生する売却益など、企業がどんな資産を所有して、どんな運用益を得ようとしているのかが分かります。
BS(貸借対照表)では、お金の「入り口と出口」「調達と運用」といった、企業の本質を分析することができます。
PL/損益計算書
BSで書かれている資産や負債以外にも「お金の流れ」は存在します。
ビジネスをする上で最も大切な項目は「売上」であり、売上に必要なのが「仕入れ・水道光熱費・給与・費用」などの経費です。
PLで重要になる言語は「売上総利益・営業利益・経常利益」の3つです。
- 売上総利益…1年間で得た収益(売上高)ー売上原価(仕入れ)
- 営業利益…(売上総利益)ー(販売費・一般管理費)
- 経常利益…(営業利益)ー(営業外収益+営業外費用)
営業利益は企業が事業によって得た利益であり、経常利益は企業が得た全体の利益といった違いがあります。
PL(損益計算書)では、企業が1年間で得た収益の内訳がわかり、企業全体の利益がいくらなのか見ることができます。
考察&感想
本書を読むことで社会人に必須のリテラシーとして、「会計学」の基本知識を学ぶことができます。
実際に読んでみて、BS(貸借対照表)とPL(損益計算書)が重要であり、BSを見るだけで企業の資産や負債を知ることができます。
日常で会計学をどう役立てるか?
本書では、BSとPLを主に学びましたが、果たして日常生活において「会計学」をどの様に役立てていけばよいのか考えていきます。
基本的な会計学を学んだところで、実際に使える場面が無いと意味が無いため、一般的なサラリーマンに当てはめて考えていきます。
ほとんどのサラリーマンのBSを見ると、右上の負債と左側の資産が0、給料から生活費を引いたのが純資産となり、左側は「現預金」となります。
資産が現預金だけの場合、当然リスクがあるため様々な資産を所有することが大切です。
今後の課題は、親から「貯金しなさい」と言われ続けてきたから貯金をするのではなく、貯金をしながら株式や不動産といった資産に変化させることです。
純資産の形を変える大切さ
BSやPLという言葉は、簿記を勉強していたときに聞いたことがあるくらいであったが、本書を読むことで2つの財務書類を理解することができました。
特に、「企業はどんな資産を所有しているのか」がわかる資産と負債のバランス、「企業は儲かっているのかいないのか」がわかる売上と費用を差し引いた利益が分かりやすく解説されています。
実在する企業を例や図解を用いて説明されているため、数字が苦手な人でも会計学の全体像を掴むことができます。
この本は、会計知識をざっくりと学ぶことで、ざっくりと決算書が読めるようになりますので、投資や経営に興味がある方におすすめです。
まとめ
会計学には英語と同じように言語が重要であり、BS(貸借対照表)とPL(損益計算書)があります。
- 貸借対照表…資産と負債のバランスを表した計算書
- 損益計算書…企業が売り上げた収益や企業全体の利益と経費を表した計算書
日本では、まだまだ貯金のみのバランスシートの方が多い飲印象だが、資産が現預金だけではリスクが高いため、できるだけ株や不動産といった資産に形を変化させていくことが重要です。

最後までご覧いただき感謝です!

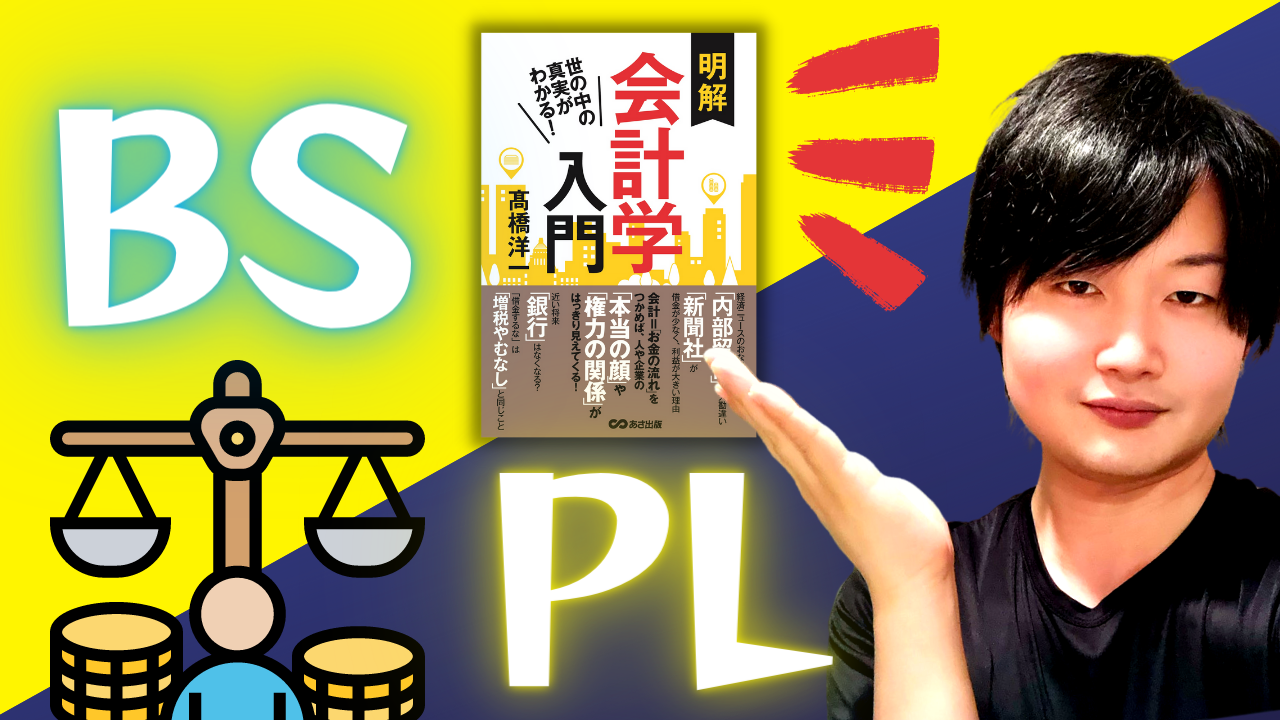



コメント