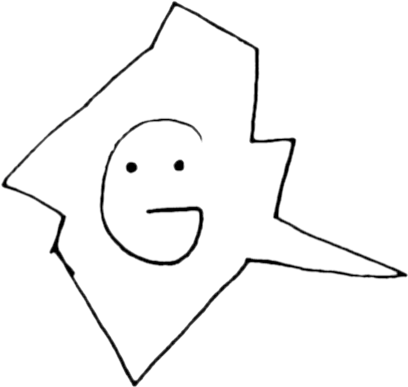
今回は、大村大次郎さんの著書「教養として知っておきたい33の経済理論(彩図社)」の書評だヨ
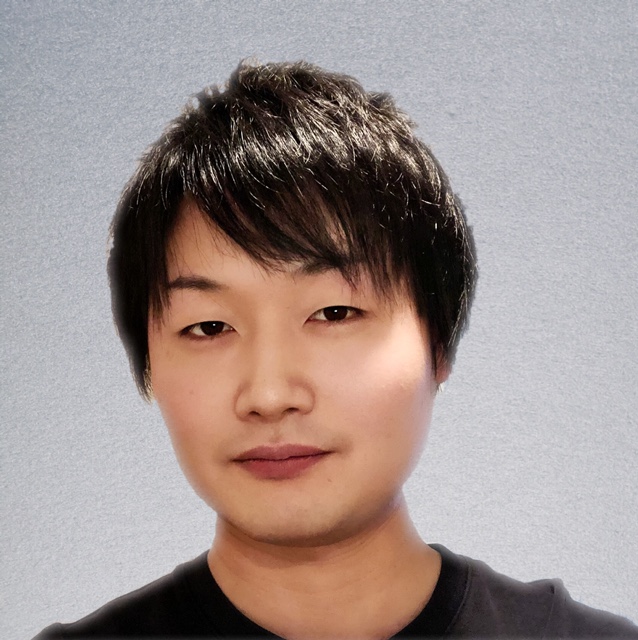
「適切なリスクヘッジを取ることで得する人になる」でお馴染みの群馬俊貴です!
- 自分で判断するのが苦手である
- 他人の意見に流されてしまいがち
- 経済学に少しでも興味がる
経済学=住みやすい社会を作る
経済学や経済理論は、大学で経済学を専攻した人以外はピンとこない人も多いですが、いわゆるマーケティングや行動経済学として、日常生活に影響する知識のことです。
例えば、ドラッグストアへ化粧品を買いに行った場合、思わず有名な芸能人が出演している化粧品を手にとってしまうのは、ハロー効果と呼ばれる心理学が働く影響です。
上記のような経営学を学ぶことにより、社会の仕組みを解き明かして、より良い日常生活を過ごすことができます。
最後通牒ゲーム
「人間は損を嫌う生き物であり、他人が得するのも嫌う生き物である」ということを証明したのが、最後通牒ゲームという実験です。
Aさんに100ドルを渡し、Bさんが納得する金額をAさんが提示しないことでBさんが拒否した場合には、AさんもBさんもお金を貰えないという実験。
実験結果は、多くの被験者は40ドルから50ドルと約半分の金額をBさんに提示し、20ドル以下を提示したのは4%の人だけでした。
理由は、自分が受け取るより少ない金額をBさんに提示してしまうと、「Aさんが自分より多く貰うことが許せない」ことで自分が損をしてでも道連れにしてしまうからです。
「人間という生き物は、自分が損をしてでも他人の得が許せない生き物である」ということを証明しました。
プロスペクト理論
100円を儲けることよりも100円を損することを恐れてしまう様に、人間は損を恐れてしまうのは、プロスペクト理論による損失回避の法則が働いてしまうからです。
ダニエル・カーネマンさんの著書「ファスト&スロー」では、コイントスをして表が出たら150ドル貰えて、裏が出たら100ドル失ってしまうという実験が書かれています。
多くの人はこのギャンブルを断り、150ドルを儲けることよりも、100ドル失ってしまう損失の方を優先してしまうことが分かりました。
この様に、人間は極端に損失を恐れる生き物であり、本能に近い感覚でリスクを避けてしまいます。
3つの視点から分析
私が、分析した3つの視点「観察・考察・推察」は以下の通りです。
- 観察…人間は得よりも損に影響されやすい
- 考察…リスクヘッジをとれば行動できる
- 推察…損失の妥協点を低く設定して無敵になる
観察
人間は損を極端に嫌い、他人が得することさえ嫌う面倒な生き物です。
最後通牒ゲームでも説明した通り、Bさんは本来もらえないお金をもらうことができるのにも関わらず、Aさんの方が多くもらう様なら道連れにしてしまいます。
行動経済学であるプロスペクト理論の、「損失回避の法則」が働くことにより、人間は損を避けてしまうことが分かります。
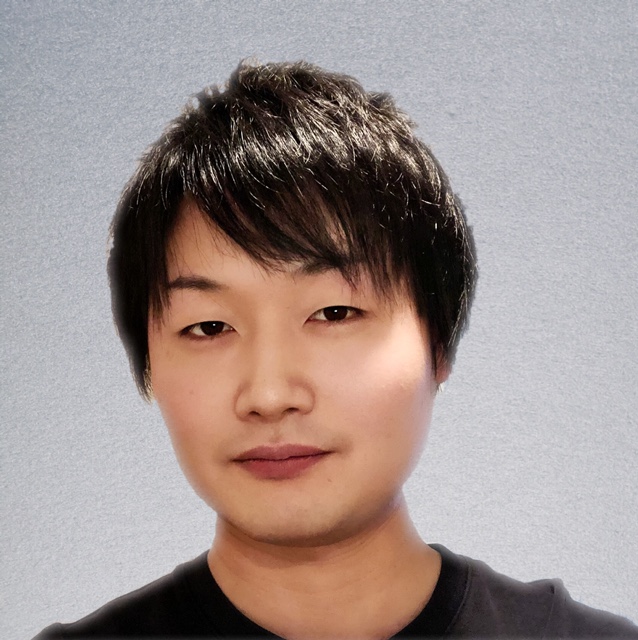
人間は損を避ける性質があります。
考察
損失を避けてしまう性質を、起業やビジネスを起こす上で、どの様に改善していけば良いのか考えていきます。
損失を避けてしまう理由は、適切なリスクヘッジが取れていないからであり、逆を返せばリスクヘッジさえとることができれば行動の範囲は広がります。
損失回避の法則を打破するためには、適切なリスクヘッジを取ることが必要不可欠であり、「多少は損をしても見返りが大きい」という状態を作るのがベストです。
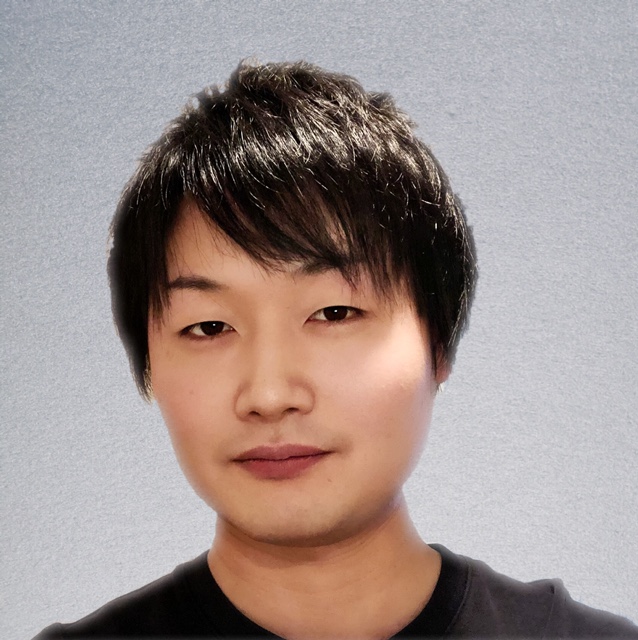
リスクヘッジをとれば行動範囲は広がります。
推察
損失を避けないためにリスクヘッジをとることで、得する方向へ舵を切ることができます。
よくニュースで取り上げられている事件の犯人というのは、失うものが1つもない「無敵の人」であるからこそ、損失が全くない状態で行動範囲が広がっています。
「得する人」になりビジネスを成功させるためには、無敵な状態を作ることが大切で、損失の妥協ラインをなるべく低く見積もることが重要です。
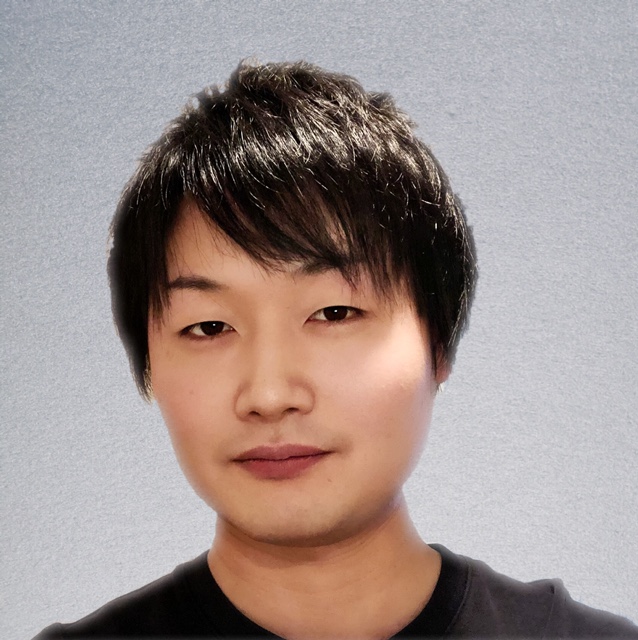
損失の妥協ラインを低く設定して無敵の状態になるのがベスト。
まとめ
経済学や経済理論は、私達の暮らしをより良く過ごしやすい社会を作ることで、社会の仕組みを把握することにより、損することを防ぐこともできます。
最後通牒ゲームやプロスペクト理論からも説明した通り、人間は損を極端に嫌い、他人が得することでも損を感じてしまう面倒な生き物です。
- 損失は避けて通ることはできない
- 行動するためにはリスクヘッジをとる
- 損失の妥協ラインを低く設定
以上の3点を意識して、「損失回避の法則」を上手くコントロールしていくことが重要です。
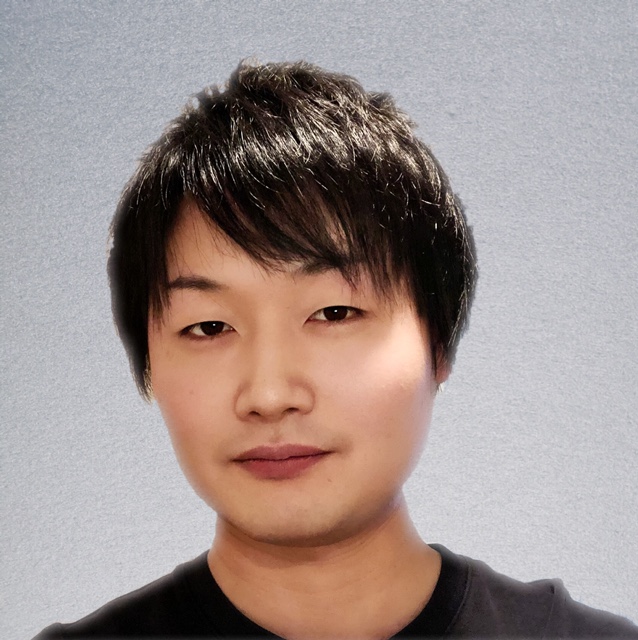
最後までご覧いただき感謝です!

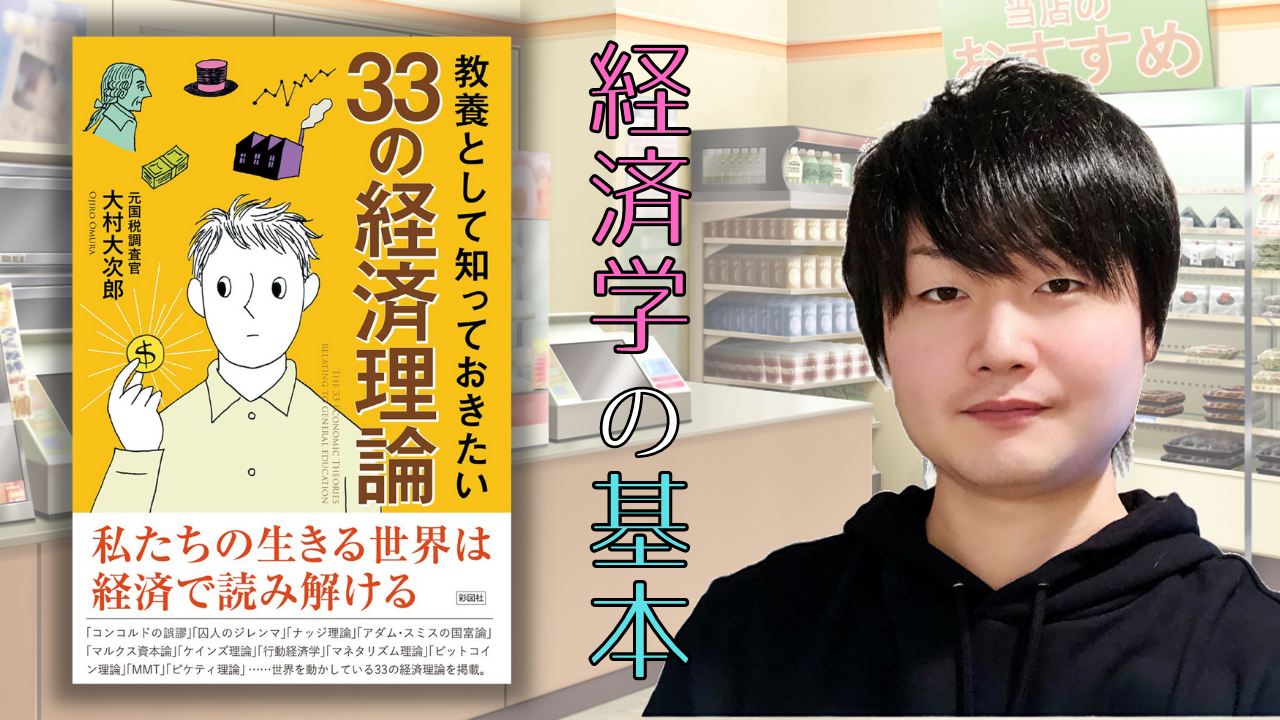



コメント