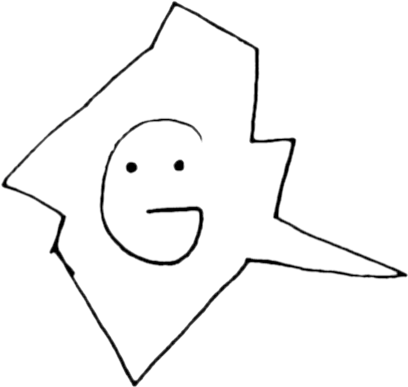
金融知識が無くて悩んでない?
- GDPの意味など経済について学びたい
- お金の流れを理解したい
- 金融リテラシーを高めたい

今回は、森永康平さんの著書「誰も教えてくれない お金と経済のしくみ」(発行:あさ出版)を書評していきます!
- お金の成り立ちから学びたい
- GDPの意味を知っておきたい
- インフレとデフレを理解したい

3分程度でサクッと読めるので、ぜひ最後までご覧ください!
GDPの意味とインフレ・デフレ
まず始めに、金融知識を高めるためには「お金の成り立ち」から理解する必要があります。
はるか昔、山の住人と海の住人が、それぞれ肉と魚を物々交換を行う様になり、売買のタイミングがマッチングしないことから、時間やルールを決めて集まって売買したのが市場の始まりです。
肉魚は時間が立つと腐敗してしまうため、やがて保存できる稲となり、貝や石、布、貴金属へ変化し、貴金属はすり減ってしまうため、紙幣が誕生しました。
GDPの意味を簡単に解説
「日本は世界第3位の経済大国」というのを耳にしたことがある方も多いですが、2007年の時点では世界第2位であり、中国が急成長を遂げて2位となり、2010年に日本は第3位となりました。
余談ですが、バブル時代の日本は、山手線の内側の土地だけで米国全土が買えるとも言われていました。
「何が第3位なのか」というと、GDP(国内総生産)をランキング化したものですが、GDPを簡単にわかりやすく解説します。
GDPとは、一定期間内で新たに生み出されたモノやサービスの付加価値の合計です。付加価値とは、商品が店頭に並ぶまでには段階があります。原材料メーカーが加工業者へ原材料を売り、加工業者が小売業者へ加工食品を売り、小売業者が消費者へ商品を売ります。それぞれの、原材料メーカー、加工業者、小売業者は、売る際に利益という付加価値を上乗せして販売します。
原材料メーカー、加工業者、小売業者、3者の利益を合計した額がGDPです。
インフレとデフレの違い
インフレとは、インフレーションの略であり、物の値段が上昇し続ける状態であり、インフレには「良いインフレ」と「悪いインフレ」の2種類があります。
- ディマンドプル・インフレ…景気が良くなり消費者が物を買い続けるため、徐々に物価が上昇する(良いインフレ)
- コストプッシュ・インフレ…原材料の値段が高騰するに従って物価も上昇する(悪いインフレ)
デフレとは、デフレーションの略であり、物価が下がり続ける状態です。
例えば、リーマンショックやコロナウィルスなどの要因によって景気が悪くなり、消費者が節約して物を買わないため、企業は物を売るために物価を下げます。
物価が下がるからといって「ラッキー」と思った方は、一部の視点でしか見ていないと著者の森永さんは述べています。
多くの人は「消費者」でもあり「労働者」でもあるため、企業の商品が売れなければ、人件費を削減して利益を作るしかないため、ボーナスカット、昇給見送り、最悪の場合はリストラも有り得ます。
人件費削減により給料が減り、給料が減るため節約し、商品が売れないため物価を下げる、商品が売れないから人件費削減、といった様に負の連鎖に陥ってしまうことをデフレスパイラルです。
考察&感想
本書の目的は、金融知識について乏しい日本人1人1人が、お金の知識と教養を身につけることで、日本をより良い国へと近づけることができることです。
実際に読んだ結果、浪費と消費の違いや、お金を「使う・貯める・増やす」などの金融知識を学び、経済の仕組みを基礎から学べました。
インフレとデフレどっちが良い?
本書では、デフレのデメリットとして、デフレスパイラルが恐ろしいと説明されていましたが、果たしてインフレとデフレは、どちらのほうが良いか疑問に感じました。
インフレのメリットは、円安となることで輸出が好調になったり、外国の観光客が増えることであり、デメリットは、輸入品が高くなり海外旅行の費用が高くなることです。
デフレのメリットは、お金の価値が上がり、安く物が買えることで、デメリットは、給料が減りリストラが増えて土地などの資産価値も減ってしまうことです。
私個人の意見としては、インフレの方が経済的には良いと考えています。
なぜなら、インフレ時には、海外からの観光客が多く訪れたり、日本株が多く買われたり、経済的には良い方向へ進んでいくと考えているからです。
コストプッシュインフレ(景気が悪いインフレ)の対策としては、企業で働く従業員に賞与や昇給でモチベーションを高めて、物価の上昇で得た利益の一部を従業員へ還元するとともに、個人の資産形成も意識していかなければなりません。
金融リテラシーが高まる!
本書を読むことで、お金の成り立ちから金融知識、経済の仕組みが学べるため、「お金について悩んでいる人」に大変おすすめできる1冊です。
本書は、金融や経済について初心者にも優しく説明されているのため、ある程度金融リテラシーがある人にとっては、少々物足りなさを感じてしまう恐れがあります。
しかし、逆を返せば、初心者にとっては金融や経済を学ぶ上でのきっかけにもなり、より多くの日本人の金融リテラシー向上にも繋がるとも思いました。
幅広いジャンルから金融について学ぶため、ややこしくなってしまいますが、多くの視点から金融や経済の基本知識を学べるため、個人的には大変おすすめできる読みやすい書籍でした。
まとめ
GDPとは国内総生産のことで、原材料メーカー、加工業者、小売業者の3者がそれぞれ付加価値という利益を上乗せして販売していき、3者の付加価値(利益)を合計したものです。
インフレは物価が上昇している状態であり、デフレは物価が下がり続けている状態で、インフレには「ディマンドプル・インフレ(良いインフレ)」と「コストプッシュ・インフレ(悪いインフレ)」があります。
デフレ時には、給料が減って人々が節約して物価が下がり、物価が下がって給料を減らし人々が節約するという、デフレスパイラルに陥ることが最も恐ろしいデメリットです。
本書では、金融や経済を幅広い視点から学ぶことで金融リテラシーを高められるので、お金について悩んでいる人はぜひ読んでみてください!

最後までご覧いただき感謝です!





コメント