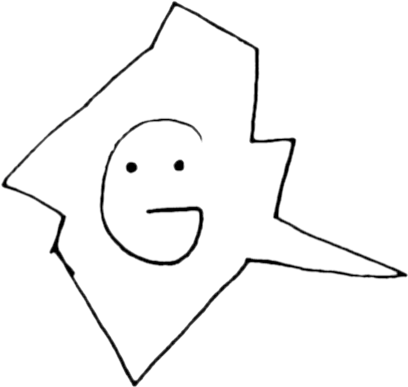
株式投資について悩んでない?
- 投資に興味があるけど不安
- 投資で損をするのが怖い
- 売買のタイミングがわからない

今回は、中桐啓貴さんの著書「日本一カンタンな「投資」と「お金」の本」(発行:クロスメディア・パブリッシング)で解決します!
- 株式投資に興味があって挑戦してみたい
- 投資で損をするかもと不安に感じる
- 売買のタイミングについて学びたい

3分程度でサクッと読めるので、ぜひ最後までご覧ください!
行動ファイナンスを学んで損失回避
投資とは、企業に投資することで事業が成長すれば、企業からのリターンを得られるだけでなく、企業間の競争から新たなイノベーションも生まれやすくなります。
投資とは、短期的に儲けるのではなく、長期的な成長とともにリターンを得る、資本主義をより豊かに生きるための行為なのです。
投資で損失を回避するためには、行動経済学を投資理論に落とし込んだ行動ファイナンスを学ぶことが重要であり、下記の3点を簡単に説明していきます。
- プロスペクト理論
- アンカリング効果
- 楽観主義に注意
プロスペクト理論
プロスペクト理論とは、人間は誰しもリスクを回避したがる特性があるということです。
例えば、Aの選択肢では確実に1万円を損して、Bの選択肢では50%の確率で損せず50%の確率で2万円を損する場合、多くの人は後者であるBを選択します。
人間は誰しも利益よりも損失の方を重要視しがちで損失を回避してしまうため、「今日その株をもう一度買いたいか」よく考えて、答えがNOの場合には買うべきではありません。
アンカリング効果
アンカリング効果とは、人間は最初に見た数字だけで判断してしまうことであり、過去の情報に惑わされて投資判断をしてはいけません。
例えば、スーパーに買い物へ行った際、1500円の和牛ステーキが半額で売られていたら、夕食のメニューを決めていたにも関わらず、「安いから」という理由だけで買ってしまいます。
投資も同じで、「過去の株価が高かったから必ずこの価格まで戻るだろう」と考えずに、企業の価値を現時点での情報を元に将来性を判断することが大切です。
楽観主義には注意
投資をする上で楽観主義ではなく、悲観主義であるべきことが大切であり、楽観主義と悲観主義の定義として、本書では以下の通りに述べられています。
- 楽観主義…50%の確率であれば勝つだろうと考える
- 悲観主義…50%の確率であれば負けるかもしれない
楽観主義のデメリットは、投資に対して自信過剰になってしまい、過剰なリスクをとってしまいます。
投資する上で大切なのは、投資する企業の情報をよく調べた上で慎重に判断し、きちんと適正なリスクをとる悲観主義であることです。
考察
本書では、行動ファイナンスを学ぶことにより、投資する上で少しでも損失を回避することが説明されています。
そこで、目先の数字に惑わされてはいけないことと、悲観主義である必要があります。
売買の判断はどうやってするべきなのか?、楽観主義と悲観主義では本当に悲観主義であるべきなのか?を考えていきます。
売買の判断はどうすれば良い?
過去の数字で判断してしまうアンカリング効果を防止するためには、適切な売買を行わなければなりません。
例えば、オークションでレアな商品を買う理由として、「過去に限定的に発売されたから」「将来的に絶対に価値が高くなるから」などで判断してはいけません。
株式投資においても、目先のデータに囚われず、自分が本当に納得できるポイントを明確にした上で、売買のタイミングを判断すべきです。
楽観主義と悲観主義どっち?
株式投資において楽観主義で自信過剰になるよりも、悲観主義で慎重に適正なリスクを取るべきだと説明されていましたが、果たして本当に悲観主義が良いのでしょうか。
適正なリスクを取れる点では悲観主義であるべきですが、悲観主義のデメリットとして、最後の一歩が踏み出せないことが上げられます。
適正なリスクはとれているのにも関わらず、最後の「買う」というステップで踏み込めないため、最終的にリターンを得ることができません。
投資で確実にリターンを得るためにも、適正なリスクを取る悲観主義で積極的に行動できる「積極的な悲観主義」であるべきです。
まとめ
株式投資において損失を回避するためには、行動ファイナンスを学び、人間の特性を理解する必要があります。
投資する上で大切な行動ファイナンスは
- プロスペクト理論で特性を知る
- アンカリング効果による目先の情報に囚われない
- 悲観主義で適切なリスクをとる
以上の3点です。
現状での企業の価値を調べて「本当にこの株が買いたいか」よく考えた上で、適切なリスクをとって株式投資に挑戦してみてください!

最後までごらんいただき感謝です!



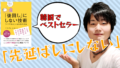

コメント