
「残業が当たり前は危険信号」でお馴染みの群馬俊貴です!
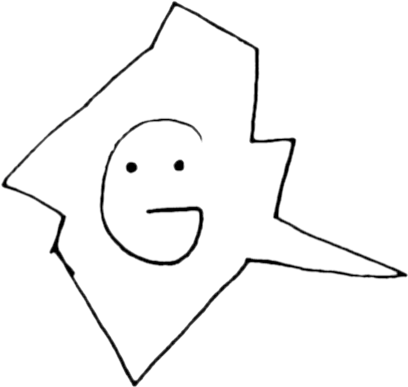
今回のテーマは「残業は”少数の法則”による洗脳」だヨ
「残業するのが当たり前」「皆も頑張っているから頑張らないと」と言ったように、残業=頑張っている証拠と考える方も多いです。
実際に残業している従業員が上司から評価されるのも事実で、昭和の日本が作り上げた古き悪き日本の習慣の1つです。

残業で悩んでいませんか?「残業しないと評価してもらえない。皆が残業してるから頑張らないといけない。自分だけ定時退社すると罪悪感がある。」
周りの従業員が残業をしている場合「少数の法則」という心理現象が働く事により、「自分も残業しなければ」と考えてしまいます。
残業してしまうのは決して自分のせいではなく、心理現象による影響が強い事になります。
今回は、残業するのが当たり前と洗脳されてしまう理由を、少数に法則に基づいて説明していきます。
- 残業は「少数の法則」による洗脳
- 身近な環境が「普通」だと錯覚
- 理由を付けて納得してしまう

詳しくはスクロール!
残業は「少数の法則」による洗脳
残業が当たり前と考えてしまうのは、少数の法則という心理現象の影響です。
例えば、勤めている会社の従業員数が100人が在籍しているとします。自分が配属されている部署の人数が5人のうち4人が残業している場合、全体で見ると少数なのにも関わらず「残業しなければいけない」と判断してしまいます。
この様に、全体的に見た時の割合とは圧倒的に少ない例だけで、物事を判断してしまうことを「少数の法則」と言います。
「残業が当たり前」と考えてしまうのも、自分の周りの少数だけで判断することにより、残業する人は頑張っている証拠だと解釈してしまいます。
私が落語家の見習い弟子として活動していた時、寄席の楽屋では師匠との雑談は許されませんでしたし、食事の際には残飯処理するのが普通でした。この様なルールは、落語の世界だけのルールですが「少数の法則」により当たり前だと考えてしまいました。
「少数の法則」とは、自分が気が付かないうちに洗脳されてしまい、目の前の世界が普通であると判断してしまう心理現象を避けられません。

人間は目の前のルールに縛られてしまいます。
身近な環境が「普通」だと錯覚
人間は環境に適応しようとする習性があるため、目の前が異常な環境だったとしても、身近な環境を「普通」だと錯覚してしまいます。
自分の部署の環境だけで判断するにはデータが少ないのにも関わらず、身近な環境が普通だと思い込む事で「残業するのが当たり前だ」と判断してしまいます。
身近な先輩や同僚など、距離が近い少ないデータが全体のデータだと思いこんでしまいます。
例えば、自分の所属する部署の半数以上が残業しているからといって、会社全体で半数以上が残業しているとは限らないという事です。
人間が物事を判断する基準として、目の前の身近な環境が「普通」であると錯覚してしまいます。
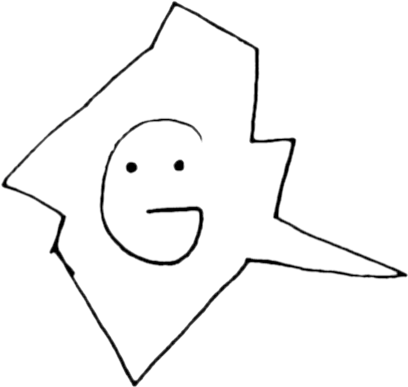
身近な環境が当たり前ではないと思うのが重要だヨ。
理由を付けて納得してるだけ

少数の法則により残業をしている状態は、何かと理由を探して残業を正当化しようとしています。
心のどこかでは「定時退社して趣味を楽しみたい」と思っていたとしても、少数の法則が働く事により納得せざるを得ません。
「皆も残業して頑張っているのだから自分も頑張らなければ」と気合いで誤魔化しているだけに過ぎなく、残業しなければ上司からの評価も得られないため、残業を選択してしまいます。
残業しないと上司から評価してもらえないと考える方も多いですが、残業しないと評価してもらえない訳では無く、残業しないで評価されている人のデータが少ないため誤った解釈をしているだけです。
「残業している人」と「残業していない人」とでは、データの量に圧倒的な差がありすぎて比べられないのにも関わらず、残業をする理由をつけて納得してしまいます。

人間は2つのデータに差があっても理由をつけて納得してしまいます。
退職も1つの選択肢である
残業しないと評価が得られない会社から脱却するための選択として、退職は重要な選択肢の1つです。
退職と聞くとハードルが高く感じてしまう方も多いですが、退職することで給料があがったり、定時退社により自分の時間が増えたりといったメリットも期待できます。
働く時間が減って給料が高くなる可能性も十分に期待できるため、スキルアップや高待遇を求めるための退職という選択肢も必要になります。
「自分から退職を伝えられない」や「上司が怖くて退職を言い出せない」という方々におすすめのサービスが「退職代行サービス」です。
自分の代わりに退職を会社に伝えてくれるサービスです。弁護士が運営している業者であれば、未払い残業代や有給消化の交渉も行うことが出来ます。
退職代行サービスについて詳しく知りたい方は、【退職代行サービス】「弁護士在籍」と「非弁」どっちがおすすめ?で説明してますので是非ご覧ください。
まとめ
「残業するのが当たり前」という感情は、少数の法則の心理現象が原因であり
- 目の前の少数のデータを信用してしまう
- 身近な環境を「普通」だと錯覚
- 理由を付けて納得してしまう
これらの影響により、「皆も頑張っているから自分も残業しなければならない」と納得せざるを得ません。
たしかに、残業することを全面的に否定は出来ませんが、趣味の時間や勉強の時間を確保したい場合に限っては、残業を強いられる職場は弊害でしかありません。
残業をすることによって、知らず知らずのうちにストレスが蓄積してしまい、病気になってしまうリスクも生じます。
残業する際には、残業することで得られるメリットと生じるデメリットを良く把握した上で判断する必要があります。

最後までご覧いただき感謝です!






コメント