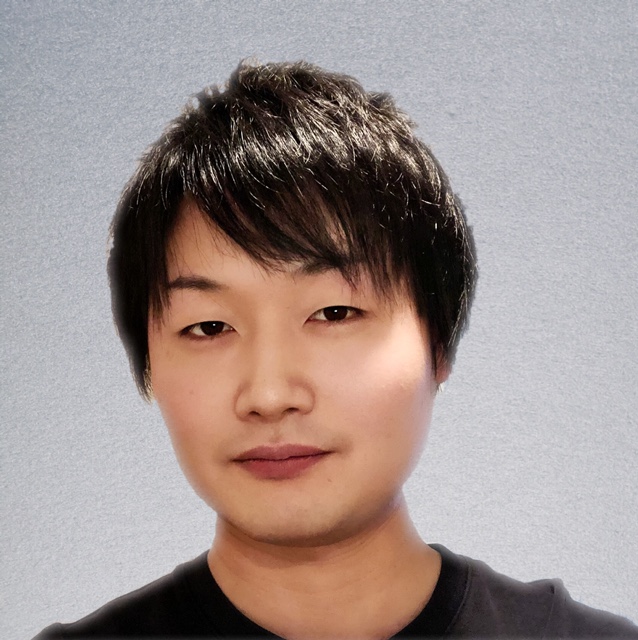
「落語家の弟子は雑用係」でお馴染みの群馬俊貴です!
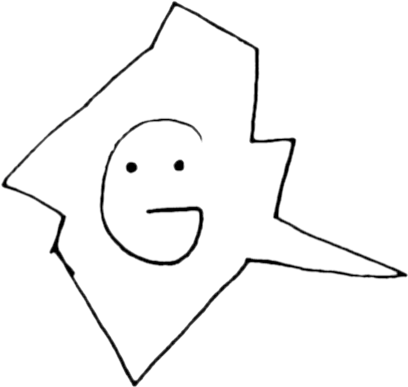
今回のテーマは「落語家に弟子入りする前に知っておきたい現実5選」だヨ
「落語家に弟子入りしたい!」と決心しても常に付きまとうのが「不安」です。
「弟子として入門した後には一体どの様な修行生活が待っているのだろう」とワクワクすると同時に不安感も高まり、中にはイメージで大変そうと決めつけて諦めてしまう方もいらっしゃいます。

落語家の弟子について悩んでいませんか?
- 入門したらどの様な生活が待っているのか不安
- 諦め癖があるけど続けられるか不安
- 常に師匠と行動を共にしないといけないのか
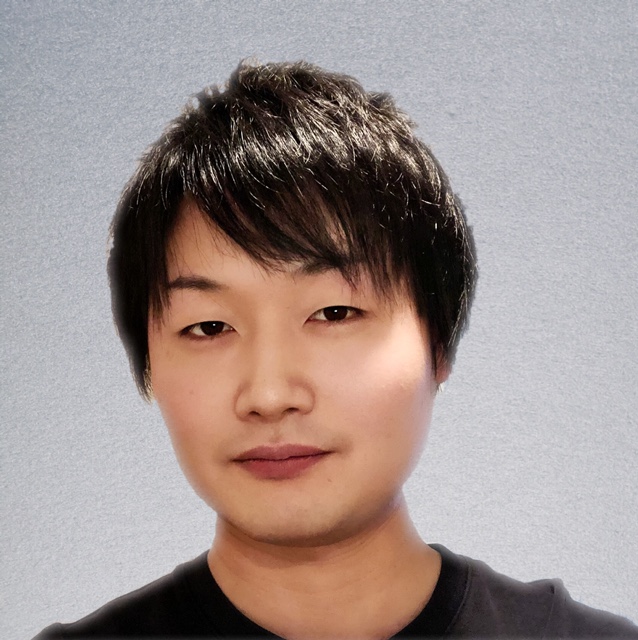
予め修行内容を知っておけば準備ができて安心します!
私は、高校卒業後に在学していた芸能マネージャーの専門学校の就職活動に難航していたことから、最終的には某落語家に弟子入りして約1年の修行生活を行いました。
なぜ芸能マネージャーから落語家の道へ進む決心をしたかというと、単純に現在でも師弟制度がある落語の世界が面白そうだったからです。
興味があるという軽い気持ちだけで入門した私がいる様に、しっかりとした理由がなくても十分に弟子入り可能だということをお伝えしたいです。
- 弟子入りに土下座は時代遅れ
- 見習い弟子の具体的な修行内容
- 見習い弟子で体験したエピソード
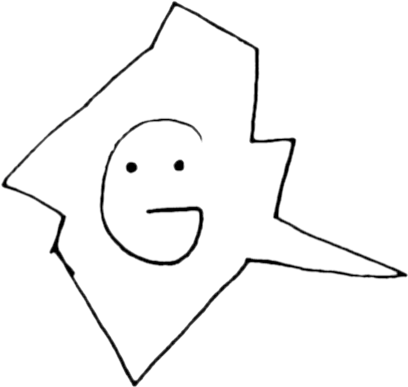
詳しくはスクロール!
弟子入り前に知っておきたいこと5選!
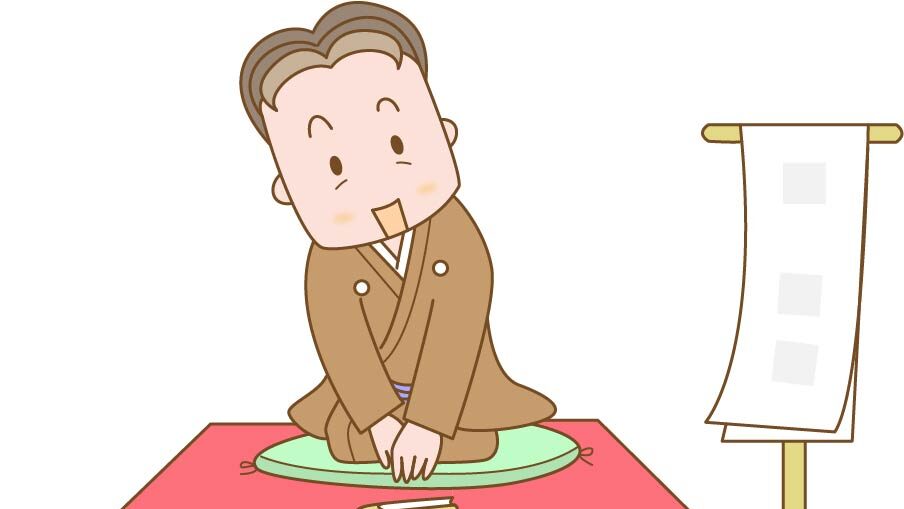
落語家に弟子入り志願する直前は、緊張と不安でいっぱいになるのは当然であり、私自身も弟子入りを決めた際は興味本位の気持ちもありましたが「人生を落語に捧げる」諦めに近い感情を抱いたのも事実です。
今回の記事を読んで、落語家の弟子のイメージを想像していただき、少しでも不安を解消することができれば嬉しいです。
弟子入りに土下座は時代遅れ
ドラマや映画の影響から、弟子入り=土下座というイメージが強く、どうやって弟子入りしたら良いかわからない方も多いです。
私の場合、浅草演芸ホールで弟子入りしたい師匠の落語を見終わったら、外で出待ちをして出てきたところを見計らって弟子入り志願しました。
弟子入り志願は浅草演芸ホールがおすすめで、新宿の新宿末廣亭だと正面と裏口が存在して、せっかく足を運んだのにすれ違いなんてこともありえます。(実際に出待ちしましたが失敗しました)
【体験談】落語家に弟子入りする方法は「寄席の出待ちで直談判」
見習い弟子の具体的な修行内容
入門したての見習い弟子の修行内容は、落語を覚えるよりも、師匠と共に様々な現場に同行したり、師匠宅の掃除や雑用がメインの修行内容です。
掃除や雑用の合間にできた暇な時間に、落語、着物のたたみ方、太鼓のたたき方を師匠や兄弟子から教えてもらいます。
落語を覚えるのには自主練習がとても重要で、私自身も自宅の鏡の前で何度も落語を練習していました。
大変だったことはアルバイト
落語家の弟子となる形態は2種類あり、師匠宅に住み込みで徹底的に学ぶ「内弟子」と、決められた時に師匠宅へ通いながら学ぶ「通い弟子」があります。
現代では、プライベートが重視される通い弟子として学ぶのが一般的になりつつありますが、まだまだ内弟子の文化も根強いため、弟子入りする際はリサーチが必要です。
通い弟子の場合、プライベートも師匠の指示に従わなくてはならず、私の場合は基本的にフルタイムでアルバイトで働いていました。
見習い弟子は「残飯処理係」
落語家の見習い弟子は、師匠とレストランや居酒屋に行ったときに、師匠や兄弟子が残した料理を全て食べなければなりません。
私が師匠のご家族と居酒屋に行った際の出来事ですが、食べ残す前提で料理を注文するため、必然的に苦しくなるまで料理を食べさせられました。
私が入門した一門では、1番下の階級の者が残飯を食べるのが伝統となっており、苦しかったらトイレで吐き出してでも食べなければなりませんでした。
前座名は気分で決まる?!
「落語家の弟子の芸名ってどんな風に決まるの?」という方も多いですが、前座の芸名は面白くて覚えやすい芸名が命名されます。
師匠の気分次第で命名されてしまい、自分には拒否権が一切ありません。
私は、一度決まった芸名を命名されて1週間くらい経過した後に、「やっぱり辞めた」と言われ、新しい面白いユニークな芸名を命名されました。
まとめ
落語家への弟子入りは、興味本位でも入門して良いですが、事前に現実を知っておくことでイメージとリアルのギャップを少なくすることができます。
修行内容の落語、着物のたたみ方、太鼓のたたき方に関して「自分にもできるかな」と不安に感じてしまう方もいらっしゃると思いますが、私のように興味本位で入門しても苦ではありませんでした。
何故、私が落語家の見習い弟子を辞めてしまったのかというと、上下関係のルールがとてつもなく厳しかったからです。
師匠や兄弟子の言うことは絶対ですし、残した料理は吐き出してでも食べなければいけなかったり、とにかく日本の古き悪き風習が現代でも残っています。
ただし、個人個人により合う合わないがありますので、落語家に興味があるのであれば、貴重な経験を得るためにも一度弟子入りしてみるのも良い経験になります。
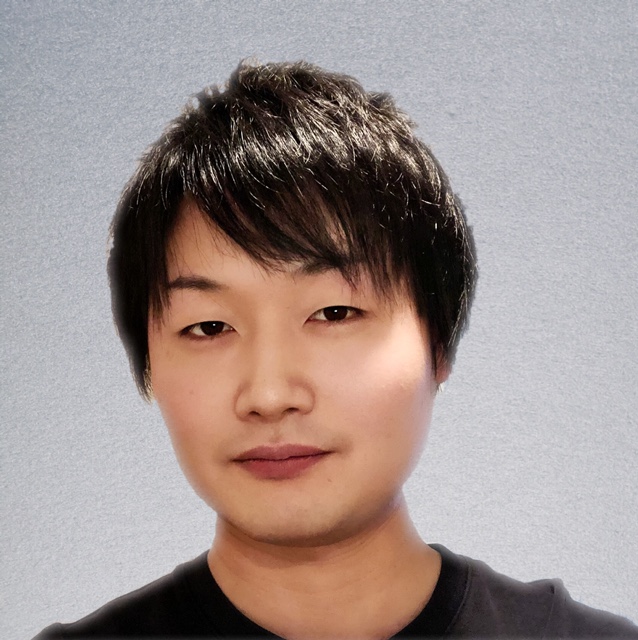
最後までご覧いただき感謝です!
落語心中は、落語に弟子入りする与太郎が一人前の落語家となって活躍するまでを描いた漫画「落語心中」は、実際に弟子入りした私が読んでも共感できてリアルな作品です。
もしも落語家への弟子入りを考えている方はぜひ一度読んでみてください。





コメント